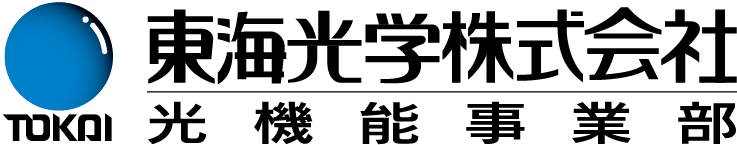基本用語解説
光の波長(Wavelength)
光には色々な波長の電磁波が存在します。「どこからどこまでを光と呼ぶか」という定義の問題は別として、一般的には
| 紫外光 | 190nm ~ 380nm |
|---|---|
| 可視光 | 380nm ~ 780nm |
| 近赤外光 | 780nm ~ 3,000nm(3μm) |
| 中赤外光 | 3,000nm ~ 30,000nm(30μm) |
と分類されており、光学薄膜で取り扱う光の波長も上記の範囲内にあります。
この中で人間の目に見える波長は可視光ですが、蛍光灯や太陽光がほぼ白色に見えるのは、すべての色がほぼ均等に混ざり合っているためで、実際には短い波長の青色から長い波長の赤色までの色が存在します。虹は水滴のプリズム作用で波長別に光が分解されるために生じます。
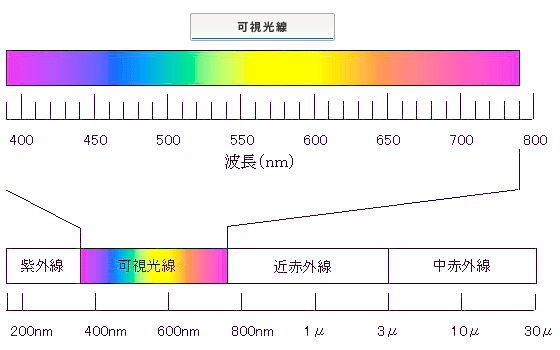
波長を示す単位としては、nm(ナノメータ)が良く用いられます。
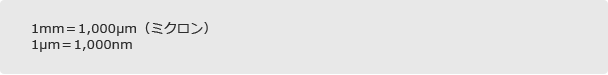
ですから、1nmは百万分の1ミリ、つまり550nmの波長の緑の光は0.00055mmの波長となります。
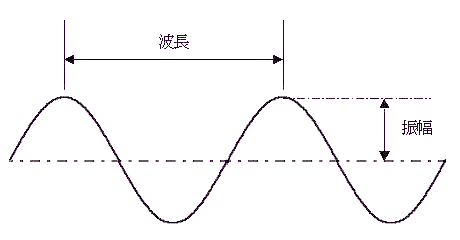
光の分散(Dispersion)
光は波長により、媒質中での速度が異なるため、同じ媒質中でも波長別に屈折率が異なります。虹が7色に見えるのも雨の水滴によって光が波長別に異なる屈折率で曲がっているためです。
波長の短い青色の光は屈折率が高く、大きく曲がるのに対して、赤色の光は青色に較べて屈折率が低いため、曲がり方が少なくなります。
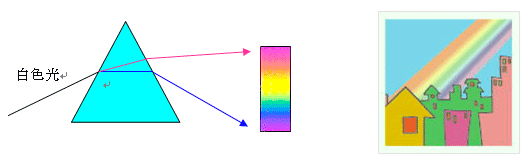
下記の図は光学ガラスの代表であるBK-7の波長分散です。短波長側で屈折率が高く、長波長側に向かって屈折率が下がっていく事が分かります。
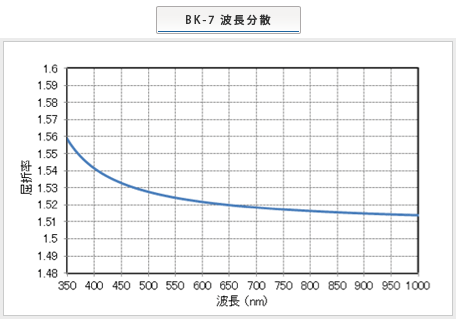
実際の光学薄膜設計においては、基板や薄膜材料の波長分散を把握する事は所望の分光特性を得るために重要な要素となります。
屈折率(Refractive Index)
屈折率(一般的にはnで表す)といいますと、多くの人がスネルの法則を思い出されることでしょう。
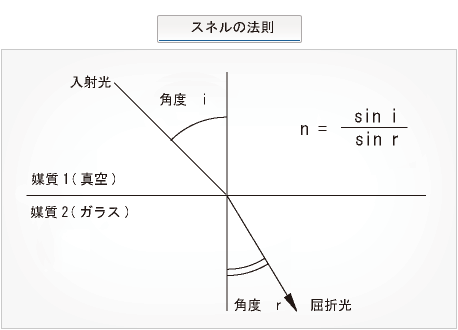
確かに分かりやすい式です。しかし、この式は光が斜め方向から入射する場合には理解しやすいのですが、光が垂直に入射してきた場合を考えると理解しにくくなります。
このため屈折率(n)とは真空中の光の速度(C)と媒質中の光の速度(V)との比と覚えておくと便利です。
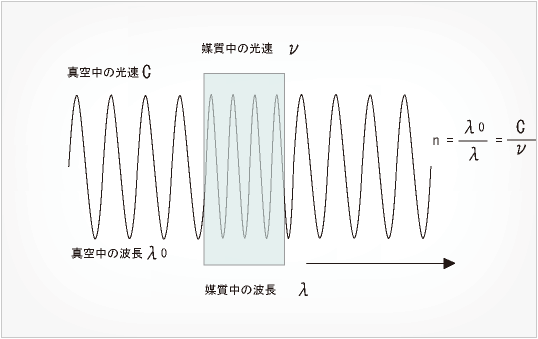
光の速度が変わると、媒質中で屈折する理由はホイヘンスの原理で説明できます。
物理膜厚と光学膜厚(Physical Thickness & Optical Thickness)
一般的に「膜厚」と言えば物理膜厚の事を言います。すなわち「物差しで測った長さ」そのものです。光学薄膜の世界では物理膜厚よりも光学膜厚を使う事が頻繁にあります。
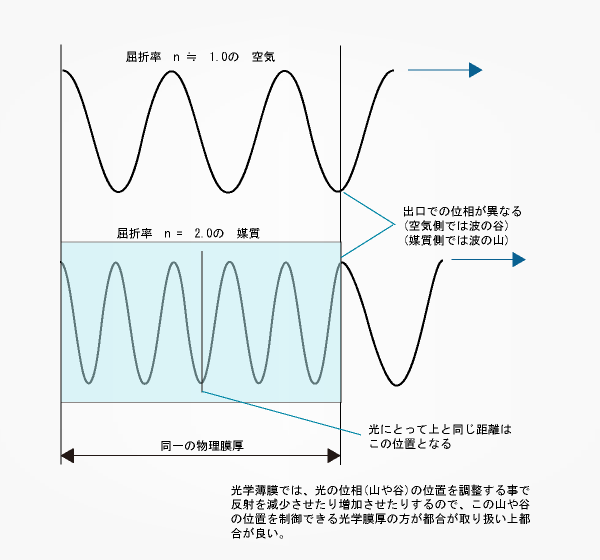
光にとって同じ厚さとは、光が同じ時間内に進める距離なのです。
一般的には、
| 屈折率 | n |
|---|---|
| 物理膜厚 | d |
| 光学膜厚 | nxd (=nd) |
で表します。
通常、光学膜厚は取り扱う光の波長の1/4の何倍であるかという記述を使用します。これは、光学膜厚1/4波長ごとに光の位相が同じになったり、反転したりするためです。
例えば波長500nmの光に対して光学膜厚100nmの場合は
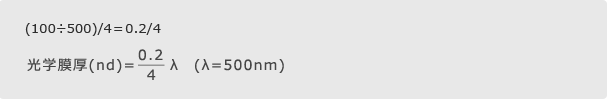
といった表記となります。
また、下記膜厚の場合、次の表記の仕方が良く使われます。
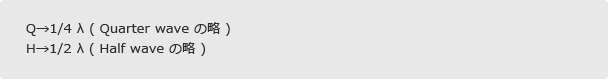
つまり、QHQの膜と言えば、次のような構成となり、基板側からの膜厚を示しています。
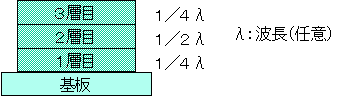
ギリシャ文字の読み方
| 大文字 | 小文字 | ||
|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | アルファ |
| Β | β | Beta | ベータ |
| Γ | γ | Gamma | ガンマ |
| Δ | δ | Delta | デルタ |
| Ε | ε | Epsilon | イプシロン |
| Z | ζ | Zeta | ゼータ |
| Η | η | Eta | イータ |
| Θ | θ | Theta | シータ |
| Ι | ι | Iota | イオタ |
| Κ | κ | Kappa | カッパ |
| Λ | λ | Lambda | ラムダ |
| Μ | μ | Mu | ミュー |
| Ν | ν | Nu | ニュー |
| Ξ | ξ | Xi | グザイ |
| Ο | ο | Omicron | オミクロン |
| Π | π | Pi | パイ |
| Ρ | ρ | Rho | ロー |
| Σ | σ | Sigma | シグマ |
| Τ | τ | Tau | タウ |
| Υ | υ | Upsilon | ウプシロン |
| Φ | φ | Phi | ファイ |
| Χ | χ | Chi | カイ |
| Ψ | ψ | Psi | プサイ |
| Ω | ω | Omega | オメガ |
お問い合わせ窓口
ご質問・ご相談など、お気軽にお問合せください。
- 東海光学株式会社 光機能事業部
- 光学薄膜
- 基本用語解説